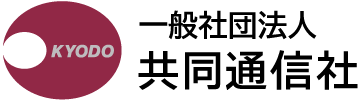長期連載‐国内
(37)もう記者は続けられない イチローと対峙した5年間
2011年秋、米大リーグでイチロー(マリナーズなど)が10年間続けてきたシーズン200安打が途切れた。スポーツ紙のイチロー番記者だった浮田圭一郎(うきた・けいいちろう)(45)は苦悩していた。応援したいのに、自らの記事でそれを表現することができない。このままでは「憧れを超えた存在」をおとしめることにならないか。
かつては自身も大リーガーを目指し、夢破れた。新たな挑戦の場に選んだ記者の仕事も、終わりを告げようとしていた。

【教諭を務める高校の教室で「番記者」時代の話をする浮田圭一郎。今でも緊張した表情を見せた=岡山県和気町】
▽洗礼
屈強な選手の鋭い打球が、瞬く間にスタンドに突き刺さる。衛星放送の中継を見た小学6年生の浮田はメジャーリーグのとりこになった。
中学から英会話教室に通った。甲子園に出場経験があり、英語教育も盛んな岡山城東高から成城大へと進んだ。野球部では、いずれも主軸を担った。大リーガーになる準備を進め、01年2月にミネソタ・ツインズとマイナー契約を結んだ。
卒業式を待たずに渡米したが、待っていたのはマイナーリーグの洗礼だった。練習は朝5時から夕方5時まで。食事や季候の違いにも苦しんだ。得意の打撃は歯が立たず、利き腕の右肘も痛めた。数試合に出場しただけの4月、チームから放出された。米独立リーグなどを渡り歩いたが、翌年8月に再び解雇された。
「手ぶらで日本には帰れない」。選手の道は閉ざされたが、現地の大学で語学やスポーツマネジメントを学び、大リーグに携わる方法を探った。
ロサンゼルス・ドジャースの通訳に採用されることになり、斎藤隆(さいとう・たかし)投手に同行する機会を得た。達成感は得られたものの「選手の気持ちが分かる自分だからこそ、その思いを引き出して表現したい」と強く感じるようになった。スポーツ紙がイチロー担当の記者を探していると知り、07年から「番記者」となった。

【囲み取材の開始を待つ「番記者」時代の浮田圭一郎(左端)=2010年9月、カリフォルニア州アナハイムのエンゼルスタジアム(本人提供)】
▽慢心
自らに厳しく、高貴。子どもの頃から憧れたスター選手への取材は、緊張感に満ちていた。的を射た質問でなければ「次の方」と流されてしまう。常に「100点」を求められているような空気に〝戦場〟を感じた。
あらゆる視点で彼のプレーを追った。マッサージを受ける回数や、打撃用手袋の色の違いなどにも注目し「体調や心境にどんな変化があったのか」と頭を巡らせた。
しかし、簡単にはいかない。「なぜネタが取れないんだ」と上司に〓(口ヘンに七)られることも多かった。ただ選手時代と同じく、人生を懸けている心地がした。「生きるか死ぬか、この感覚だ」。自分が憧れた舞台で活躍するイチローと対峙(たいじ)する日々は、厳しくも充実していた。
核心を突けるようになったのは、記者2年目のころ。1打席目に空振りした球を、2打席目で簡単に打ち返した理由を尋ねた。「名前は?」と聞かれ、答えると「浮田君、光ってるね」。ようやくイチローの視界に入ったと感じた。関係が始まった瞬間だった。
次第に距離は縮まり、翌年のオフシーズンには、単独のロングインタビューにも成功した。読者からの反響も良かった。真剣勝負の中で、イチローが自分を育ててくれている感覚があった。原稿を書くのが面白くなっていた。関係は深まっていったが、どこかに慢心が生まれ始めていた。
▽信頼
10年のシーズン後半だった。イチローの不振が続く中、各社は気を使い、取材を自重していた。浮田は使命感に駆られ、各社を代表する形でコメントを取りに行った。準備は十分ではなかった。
何を尋ねたかはよく覚えていない。イチローは「伸び悩んだね」と一言、背中越しに答えた。「新聞紙面を埋めるためだけの取材をしてしまった」。信頼を台無しにした安易な仕事を恥じた。
残り試合は、取材を自粛した。シーズン最終日に「もう一度チャンスを」と訴えた。「まあ、がんばって」。返事は一言だった。口元には笑みが見えた。首の皮一枚つながった心地がした。
翌11年、イチローは極度の不振に陥る。原因を分析する他社の記事は臆測にまみれたものばかり。同じような内容の記事を会社に要求されたが、加担しなかった。
多くの人の期待に応えるため、欠かすことなく入念に準備し、野球に向き合うイチローの姿を追い続けてきた。選手時代の自分がいかに未熟だったかを痛感させられた。憧れとともに「まるで部活の先輩」のような尊敬と親しみを感じていた。
目の前の事象だけでなく、彼の背中を押すような記事を書きたい。だが、自分の伝えたい形で紙面になることはなかった。
もう、記者の仕事は続けられないと思い、その年限りで筆をおいた。
帰国後は英語力を生かし、興味のあった教育の現場に情熱を注ぐと決めた。15年に教員免許を取り、地元岡山の高校教諭となった。「他者を本気で理解しようと努めることが大事だと学んだ」。折に触れ、米国での経験を子どもらに伝えている。
(敬称略、文・間庭智仁、写真・今里彰利、2023年10月14日出稿、年齢や肩書は出稿当時)

【照りつける夏の日差しを浴びる浮田圭一郎=岡山県和気町】