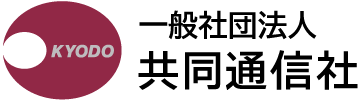長期連載‐国内
(35)生きていてもいいかな トラウマ抱えケアの道に
※この連載は5月17日に岩波書店から『迷いのない人生なんて』として刊行予定です
2021年6月、東京大4年生だった木田塔子(きだ・とうこ)(24)は、都内の病院でベッドの上にいた。
泥酔していつもより深く手首を切った。リストカットは高校生の時から。切ると意識が痛みに向き、胸がプレス機で押しつぶされるような苦しさから少し逃れられる。向精神薬を過剰に摂取するオーバードーズ(OD)や多量の飲酒とともに、心の痛みを癒やす、生き延びるための手段だ。
救急搬送され、傷の処置を受けた後、5日後に精神科に入院した。担当医は「拘束ね」と冷たく言い放った。体の自由を奪う「身体拘束」。衝動的な行動をしないようにという措置だった。
天井を見つめて、永遠に続くかと思われる拷問のような時間を耐える。訪れたのはかつて覚えた絶望感や孤独感だった。

【不忍池のほとりに腰を下ろす木田塔子。池を周遊する歩道から少し入ったこの場所が妙に落ち着く=東京・上野公園】
▽爪先立ちで
生まれた家庭は暴力が支配していた。理不尽なせっかんと、絶えることがないいさかいは、繊細な子にとって存在を脅かす虐待だった。
家族の感情を刺激しないように常に無表情で過ごし、歩くときは爪先立ちで歩く。毎晩、神様に「お願いだから助けてください」と祈った。その苦しさに、恐怖や孤独や絶望という名前があると知ったのは、ずいぶん後になってからのことだ。
勉強だけが逃げ場で、中高は有名私立女子校で過ごした。豊かな家庭のお嬢さまたちは、皆が幸せに包まれているように見えた。中学生の後半にもなると「自分が死ぬか親を殺すか」というところまで追い詰められた。
一番の理解者だと思っていた友人に、そのことを打ち明けた。帰ってきたのは「反抗期なんじゃない?」という言葉。ショックだった。「自分の気持ちは他人には、これほどにも伝わらないんだ」。もう誰にも助けを求めるまいと思った。
かたくなな決心を溶かしたのは、高1のときの担任だった。遅刻や欠席、登校しても保健室で休むことが多くなっていた木田に「どうしたの?」と尋ね続けた。
「話しても何も変わらないじゃないですか」。担任は言った。「でもあなたが話して、私が聞く、それだけで気持ちが楽になることもあるのよ」

【高校の体育祭でポーズをとる木田塔子。学校では「陽キャ」として過ごしていた=東京都内(本人提供)】
▽ケアの現場
保健室の先生は、いつも温かく迎え入れてくれた。「死にたい」。ようやく本心を打ち明けると、スクールカウンセラーにつながり、精神科にかかることになった。「話しても大丈夫な人がいるんだ」。驚きだった。
「あなたはずっと一人で生きてきたんだね」と保健室の先生は言った。「あなたには居場所がないんだよね」と医師は言った。初めて人に伝わった。幻影が映っているだけの、プラネタリウムの天井のような覆いが外れ、他者がリアルなものとして出現した。
もう一つ、木田を救ったのは学びだった。心理学や精神医学、社会学などの本を大量に読んだ。自分の心の内や、家族について考えることで、いくらか自己を客観的に見つめられるようになった。
自分の他にも傷を抱えた人はたくさんいる。そのことに気付き、吸い寄せられるようにケアの現場に向かった。炊き出しのボランティアや障害者の介助をし、大学で選んだのは看護学。自身の経験が、他者の苦しみを想像する助けになるのではないかと思う。
▽10度の入院
だが、死にたいという気持ちは相変わらず頭をもたげる。医学的には長期にわたって繰り返し受けた暴力が原因の「複雑性PTSD」という診断を受けている。
虐待のトラウマがよみがえるとき、今まさに当時と同じ状況に置かれているという痛みを感じる。いわゆるフラッシュバックだ。飲酒やOD、リストカットを繰り返し、入院歴は10回にも及ぶ。
自分が湯船だとすれば、底に穴が開いているのだと思う。だから根本的な安心感がたまらない。
穴をふさぐには「あなたは生きていいんだよ」と言ってくれる、親の無条件の愛が必要だが、もうそれは望めない。だとすれば、薬や酒に穏やかに依存し、絵や文章といった形で自分を表現しながら、何とか生きていくしかないのではないか―。
昨年から、東京都内の精神科クリニックで看護師として働き、不登校や家庭環境に悩みを持つ子どもたちの話を聞く。「泥沼に沈んでいる子には、生身のやさしさが必要だと思う」。知識や技術に頼るだけでなく、生身の人間として患者に向き合うことが、看護師という仕事だと思うのだ。
仕事にはやりがいを覚えながら、真っ黒なヘドロのような、重くて汚いものが体に詰まっている感覚が常にある。
高校生の頃まではいつも死の崖っぷちに立っていた。だが担任や保健室の先生らが手を差し伸べてくれたおかげで、今は崖の際から少し離れた地点にいると思える。
強い風には吹き戻されそうになるが、最近は迷いながらも「生きていてもいいかな」と思えるようになった。看護師として、少しでも人の心を癒やすことができるなら。
(敬称略、文・岩川洋成、写真・今里彰利、2023年9月23日出稿、年齢や肩書は出稿当時)

【不忍池のほとりを散歩する木田塔子=東京・上野公園】