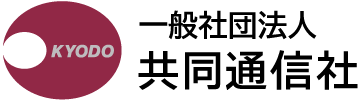長期連載‐国内
(33)生きる意味、取り戻して 乗馬で感じた風の速さに
※この連載は5月17日に岩波書店から『迷いのない人生なんて』として刊行予定です
金属バットの甲高い打球音が聞こえたのに視界からボールが消えた。気付いたときにはぼてぼてと体の真横を通り抜けて外野に転がった。草野球仲間からやじが飛ぶ中、ショートを守っていた山下泰三(やました・たいぞう)(75)=京都市在住=は胸騒ぎを覚えていた。
1985年秋、京都市内の病院で告げられた病名は指定難病の「網膜色素変性症」だった。徐々に視野が狭くなり、失明の可能性もあると男性医師が淡々と説明する。次の一言に耳を疑った。「見えなくなったとしても続けられる仕事に変えましょう」
40代手前で、勤務先の大手通信会社では営業として働き盛りだった。2人の子どもは小学生で、仕事も家庭も大黒柱として周囲を支えていく立場だった。「転職なんて考えられるわけがない」と強がったが、一歩ずつ濃い霧に足を踏み入れるように視力は失われていった。

【ヒーローは白馬に乗って現れる。子どもの頃からの憧れだった芦毛(あしげ)の感触をじっくりとたしかめる山下泰三=京都市の岸本乗馬センター】
▽割れた眼鏡
回復する可能性があるなら全て試した。酸素カプセルに視力向上の効果があると聞けば、毎週治療に通った。視野が広がる薬があると知ると、愛知県の大学病院まで行って投与を受けた。
それでも病気の進行は止まらなかった。視界はぼやけ、すりガラスを通しているように見えた。通勤時は道路の白線をたどらないと真っすぐ歩けなくなった。顔をぶつけて眼鏡が割れることもあった。
営業の仕事にも支障が出た。外勤はできなくなり、内勤で使うパソコンの画面も見えなくなった。発症から11年後、事務系の職場に異動を命じられた。左遷も同然だったが、仕方ないという思いの方が強かった。
異動初日。自分の席の名札が見えず、どこに座っていいか分からなかった。同僚に手を引かれてたどり着けたが毎回助けを借りないといけないと思うと気が重くなった。
翌日、床に何かが貼られていると足裏で感じた。同僚が席までの道が分かるよう粘着テープを貼ってくれていた。優しさに胸が熱くなった。
しかし、与えられた仕事は雑用とも言えないようなものだった。郵便物に切手を貼るだけで、10分も手を動かせば何もやることがなくなった。

【病気が進行し、仕事も休みがちになった山下泰三。自宅でも笑顔を見せることはほぼなかった=1997年、京都市(本人提供)】
▽北海道旅行
終業の時間までほとんど座っているだけなのに給料をもらい、周りから気遣いを受けることがつらいと感じるようになった。会社にとってお荷物ではないかという焦燥感も日に日に膨らんだ。
「人に世話になってばかりで何もできない不必要な存在やないか」。会社や家族のためにと居続けた場所が、自分を苦しめる場所に変わってしまった。耐えられなくなり、休職を申し出た。
家にひきこもる日々が続き、パジャマから着替える気力もなかった。妻の美恵子(みえこ)(72)は少しでも元気になってほしいと、家族旅行を提案した。子どもたちはそれぞれ北海道と沖縄県に行きたがった。
外出さえ面倒だったが、美恵子の優しさに救われる部分もあった。沈んだ気分には暖かいのは合わないと思い、北海道を選んだ。
札幌市や夕張市を訪れた後、浦河町の牧場に寄った。ソフトクリームを食べて帰ろうとしたが、美恵子から乗馬体験に誘われた。ほぼ見えない状態では断られると思ったが、牧場側は何も問題ないと受け入れてくれた。

【2005年、京都市の乗馬場で練習に励む山下泰三。自宅から片道1時間以上かけて通っていた(提供写真)】
▽挑み続ける喜び
初めて触った馬の毛は想像よりも柔らかかった。走り始めると頰で受けた風は、視力を失って以来感じたことのない速さだった。思えば、美恵子の肩を借りてゆっくり歩くことに慣れていた。
一定のリズムで響くひづめの音が心地よかった。落ちないようにと手綱をきつく握った拳から、気が付けば力が抜けていた。わずか数分の出来事だったが、笑顔が戻っていた。
旅行から帰って間もなく、完全に失明したと診断を受けた。発症から16年も過ぎ、小学生だった子どもたちも独り立ちしていた。すぐに、会社へ退職の連絡をした。
気持ちは完全に乗馬に向かっていた。患ってから燃え上がるような気持ちを抱いたのは初めてだった。「挑み続ける喜びに飢えていたんやな」
乗馬施設に通い、練習を重ねた。落馬して骨折することもあったが、やめることはなかった。けがの痛みより、生きる意味を取り戻せなくなる方が耐えられなかった。
翌年には乗馬クラブ「身体障害者馬とのふれ愛俱楽部」を設立した。参加した障害者にハンディがあっても人生の楽しみは奪われないと伝えた。
ホースセラピーについて学び、カウンセリングの資格も取得した。自分のために始めた乗馬がいつしか人のためになっていた。もう「不必要な存在」と自らを責めることもなくなった。
20年余りがたち、高齢を理由に馬に乗ることはなくなった。それでも初めて顔で受けた風の感触は、暗闇の世界の中で思い出せる。
(敬称略、文・後藤直明、写真・藤井保政2023年9月9日出稿、年齢や肩書は出稿当時)

【触れ合った芦毛(あしげ)にお礼のにんじんを与える山下泰三=京都市の京都市の岸本乗馬センター】