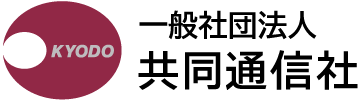長期連載‐国内
(29)確率という言葉が憎かった 諦めた夢、逆張りで再挑戦
手術前日、病室のベッドの上。がんを告知されたショックから立ち直れずにいた大津一貴(おおつ・かずたか)(33)の脳裏に、降ってくるように考えがわいた。「死ぬかもしれないなら、サッカーがしたい」。このとき22歳。既に就職して働いていた。少年時代に抱いたプロ選手の夢は、諦めたはずだった。

【サッカー教室で子どもたちを指導する大津一貴(右)。サッカーから離れることは、もう考えていない=札幌市】
▽遠い位置
中学時代、所属していた札幌のサッカークラブで頭角を現した。全国から優秀な選手を集める合宿に呼ばれ、後に有名になる香川真司や吉田麻也と汗を流した。海外で活躍するプロを目指し、強豪の青森山田高に進んだ。
365日の練習と寮生活。周りのレベルが高く、なかなかAチームに上がれない。競い合う同級生が昇格を告げられても自分は呼ばれない。結果を出そうと焦り、たまに出場しても独りよがりのプレーに。空回りが続き、次第に自信を失った。
「周りには言えなかったけど、ボールを見るのが嫌になり、気持ちは半分折れていた。高校でだめならプロは厳しいかなと」。それでも、地元を離れるとき、親や友人に背中を押してもらったことを思うと、やめるという決断はできなかった。
3年になるとようやくAチームに上がり、途中出場の機会が増えた。最後の大会、全国選手権の1回戦。1対2と劣勢の後半、ピッチに立った。
ゴール前、目の前にボールがこぼれてきた。2、3人を抜き去りシュート。だが勢いがなく、ディフェンダーに止められた。そのまま敗れ、大津の高校サッカーは終わった。悔しさの半面、ほっとした気持ちもあった。
力があれば、1年からでも抜てきされる世界。3年間、イメージした姿からは遠い位置にいることを実感し続け、もがくのに疲れていた。
大会前に進学が決まっていたため、大学でも競技を続けた。入部直後から活躍し、サッカーを楽しむ気持ちも戻ってきた。しかし、チームにプロを目指す選手はほとんどおらず、上を目指そうとは思えなかった。2012年春に会社員になり、ボールを蹴ることはなくなった。

【2006年、試合前に準備する高校2年の大津一貴。この日はベンチスタートで、出場機会はなかった(提供写真)】
▽夢物語
住宅リフォームの営業として、商談や工事の発注、現場管理など、忙しく働いた。仕事は楽しかったが、入社から約半年たった日の入浴中、違和感に気付く。片方の睾丸(こうがん)が大きくなっていた。
近所の泌尿器科を受診し、精密検査を促された。1週間後、大学病院の狭い診察室で男性医師に告げられた。「精巣がんです。若いから転移の危険がある。すぐに手術を」。頭が真っ白になり、外で座り込んだ。
「死ぬのかな」「治っても生活はどうしよう」。仕事は始めたばかりだし、いつかは結婚もしたい。でも全てはかなわないかもしれない。不安の中で迎えた手術前日、病室のベッドに横たわった。
思い返せば高校時代、自分の立ち位置や周囲のレベルを見て「プロになれるわけない」と諦めた。気持ちにふたをし、顧みないようにしてきた。大学ではなんとなく就職活動を始めてしまった。
「このまま終わりたくない」。ぼんやりと自問し、たどり着いたのはやはりサッカーだった。死を意識したことで、置かれた環境や年齢を無視して出てきた答えが「何も肉付けされていない純粋な気持ちだ」と確信した。
手術は成功したが、放射線治療の副作用が重く体重はみるみる減った。「本当に確率という言葉が憎かった。若くしてがんになることはまれだし、副作用の確率も低いと聞いていた。なんで自分ばかり」と嘆いた。
ただ、サッカーへの情熱はもう衰えなかった。歩くことから運動を始め、仕事をやりくりして社会人チームに加わった。周りに夢を語ると「現実的じゃない」「夢物語」と反対された。「でも薄い確率で悪いことばかり引くのなら、逆もある。プロになれたらヒーローだ」。そう思い、不安や焦りを乗りこえた。

【練習のためのコーンを運ぶ大津一貴=札幌市】
▽即答
それから2年余りたった。体はすっかりよくなり、全盛期の動きも戻った。14年12月、会社に黙って海外チームの関係者が集まるセレクションに参加すると、FCウランバートル(モンゴル)の監督の目にとまった。誘いを受けた大津は「行く」と即答。退社して翌春、現地に渡った。
モンゴルリーグではデビュー戦から得点を決めるなど活躍。その後、ニュージーランドやタイを渡り歩いた。18年に再びモンゴルに戻ると、以前より日本人が増えていた。サッカー協会の関係者は「君がここで活躍したから、一気に増えたんだよ」と教えてくれた。
とにかくうれしかった。「そう見てくれる人が1人でもいるだけで、やってきた意味がある」。大津は計7年間海外でプロ生活を送り、競技を離れた。今は働きながら札幌で子どもたちにサッカーを教え、海外でプロを目指す選手を現地につなぐ個人事業もしている。サッカーから離れることは、もう考えていない。
(敬称略、文・黒田隆太、写真・大森裕太、2023年8月12日出稿、年齢や肩書は出稿当時)