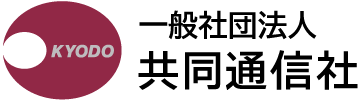長期連載‐国内
(25)共に生きる未来が見えない システム内で探った最善
去年の夏休み明けのある日、神奈川県の鶴見養護学校(今年4月に鶴見支援学校に改称)の教員、大内紀彦(おおうち・としひこ)(47)にうれしい出来事があった。「おおうちせんせい」。担任をしていた中等部1年の女子生徒が、何のヒントもなしに、初めて自分の名前を呼んだ。
女子生徒は知的障害があり、入学以来、大内の名前を言えなかった。小学校の恩師の名前と混同しているようだった。
「それが、この子が物事を覚えるペースだから」。一人一人に寄り添い、それぞれのゴールを目指して手厚い支援をする。大内は、生徒たちと過ごす毎日をいとおしく思っている。一方で、強い疑問も抱いている。

【朝、校庭で生徒たちと体をほぐす大内紀彦。この後、クラスのみんなでランニングした=神奈川県の鶴見養護学校】
▽引っかかり
36歳で特別支援学校の教員になった。大学卒業後、文化交流史の研究者を目指し、イタリアに6年間留学した末に挫折。帰国後、大学に通い直して教員免許を取った。
極端に忙しい通常学校は避けたいという思いと、障害児がよりよく生きる手助けがしたいとの素朴な正義感から選んだ。一方で、特別支援学校の役割に引っかかりを覚える自分がいた。障害児を手厚く受け入れるのは、見方を変えれば、地域の通常学校で学ぶ健常児を「邪魔しない」のが目的であるように思えた。
障害の有無で学びの場を分けるシステムに違和感を持っていても、現場ではシステムを維持する歯車の一部になることを求められる。矛盾は自覚していた。ただ、仕事にはやりがいがあった。
数年かけて一人で着替えられるようになった生徒に確かな成長を見いだす。同級生になじめない卓球好きの生徒と、毎日ラリーをして関係を築く。常に数十人の子どもと向き合う通常学校よりも、やりたいと思う教育ができる充実感があった。

【大学卒業後に留学したイタリアで、友人と街に繰り出した大内紀彦(右端)。留学先での専攻は日伊の文化交流史で、インクルーシブ教育への関心はまだなかった(提供写真)】
▽終着点
行き詰まりを感じたのは、高等部3年の担任を初めて受け持った2017年のことだ。当時勤務していた特別支援学校は、知的障害や発達障害の生徒が通っていた。1、2年時に担任をした生徒で、とりわけ思い入れがあった。
卒業後の就労先を探す必要があったが、障害が重い生徒が多く、一般企業や公的機関での就労は望みづらかった。大内は保護者や生徒と共に、地域の福祉作業所を回ることにした。作業の管理者を除くと、どこも障害者しかいない。目の当たりにして衝撃を受けた。
ボールペンを組み立てたり、ダイレクトメールを封入したり。軽作業に黙々と取り組む姿があった。教え子は健常者と関わりを持たず、それを10年、20年、30年と続ける。終着点がここならば、何のための手厚い教育なのか。
東京五輪・パラリンピックの開催に向け、障害の有無にかかわらず共に生きる「共生社会」という言葉が広がりつつあったが、目の前の現実とはかけ離れていた。しかし、就労先がなければ居場所は自宅しかない。保護者は、わが子と社会をつなぐか細い糸をたぐり寄せようと必死だった。
特別支援学校の卒業生が年々増える中、受け皿は限られ、障害が重いほど状況は厳しい。大内は、悩む保護者を励ました。苦労の末に作業所との話がまとまると、共に喜びながら、心の底に苦い思いが残った。「この手で送り出していくのか」
この年、最後まで就労先が決まらなかった生徒がいた。発達障害で気分の波が大きく、困りごとがあっても、人に助けを求められなかった。
卒業後を支える地元の役場に積極的な支援を何度も求めたが、担当者の反応は鈍い。放っておけず、知人に就労支援を頼み、障害年金を受け取る手続きを手伝った。「自分が最後のとりでだと分かっていたから。でも、助けられたとは言えない」。時折返ってくるLINE(ライン)のメッセージからは、地域でつながりを築いている様子は読み取れなかった。

【大内紀彦が一人暮らしをする川崎市の自宅を訪ねた。4人掛けの食卓にはイタリアや欧州のインクルーシブ教育に関する本や論文が山積み】
▽届く言葉を
大内はかつて留学したイタリアに再び目を向けるようになった。約50年前、障害にかかわらず地域の学校の同じ教室で共に学ぶ「インクルーシブ教育」にかじを切った先進地。今や特別支援学校はほとんど存在しない。
仕事の後、自宅でイタリア語の文献を読み込んだ。学校の中で共に学び豊かな関係を築く経験が、共生社会の実現につながる。それは決して夢物語ではないと学んだ。こんな未来もあり得ると伝えたくて、昨秋、現地のインクルーシブ教育の理念や実践を紹介する翻訳書を出版した。
読者からは「特別支援学校の方が手厚い支援が受けられる。保護者も望んでいる」と否定的な声も届く。日本の現状はその通りだと思う。でも、分けられた場所でどれだけ理想の教育を施しても、その先に、共に生きる社会はない。
文献で得た知識に血肉を通わせ、「共に学ぶなんてきれい事だ」と言う人にも届く言葉を紡ぎたい。大内は4月、イタリアの子どもたちと向き合うため、職場を1年間休職し現地へと向かった。
(敬称略、文・小田智博、写真・京極恒太、2023年7月15日出稿、年齢や肩書は出稿当時)