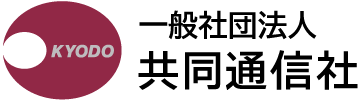長期連載‐国内
(21)つながりながら縛らない 揺らぐ職業観、引きこもる
世間でもてはやされる故郷の姿を、どこか冷めた目で眺めていた。「そんなにええもんやろか」。徳島県南部の旧海部(かいふ)町(海陽町)は10年ほど前、「自殺の発生率が全国で最も低い自治体」として一躍脚光を浴びた。
生まれ育った土地に愛着はある。ただ、内田加奈(うちだ・かな)(45)にとっては何の変哲もない田舎で、その価値が分からなかった。
海辺の小さな町だ。近所付き合いは活発だが、べたべたしていない。困っている人がいれば手助けし、人にも遠慮なく助けを求める。「右へ倣え」を嫌い、人と違っても排除されない。年長者は下の者に威張らない。
専門家は、人と人との緩やかなつながりが自殺を未然に防いでいるのではないかと分析していた。

【2023年5月、作業療法士の内田加奈(右)は依頼先の神戸市へ。相手の希望もあって、開放感のある自宅近くの須磨海岸で対話の時間を過ごした。笑顔が絶えなかった】
▽病は市に出せ
いつも多くの大人に囲まれて育った。どの家にも鍵はかかっておらず、祭りや運動会になると、身内でない人とも一緒にごちそうを囲んだ。
町には「病は市に出せ」という言い伝えが残る。悩みは1人で抱え込まず、みんなに相談しなさいという教えだ。
漁師の父と給食センターで働く母も、恥ずかしがらずに人に頼った。分からないことがあれば「あの人に聞いたらええやん」。身近な人たちの力を借りて、困り事は小さなうちに解消された。

【年に一度開かれる旧海部町の八幡祭。1980年秋、当時3歳の内田加奈(左下)は多くの大人に囲まれた(提供写真)】
内田もそれを当たり前として成長したが、自然ばかり多くてプライバシーのない環境が、若い頃は好きになれなかった。地元の高校を卒業すると町を離れ、県内の専門学校を経て1999年に京都の病院に就職した。
京都で家庭を持ち、自治会長から赤い羽根共同募金を求められた時のことだ。「うちはやりません」と丁重に断ったところ、相手が意外そうな反応を示したのが分かった。後ろめたさは感じなかったが「あ、うちだけなんやな」と悟った。
数年後、旧海部町の自殺率の低さを取り上げた本を読んで納得した。「他の自治体に比べて、赤い羽根募金が集まりにくい町」と書いてあった。
けちなのではなく、自分が納得できる理由がなければ同調しない。他者に左右されない頑固さは、裏を返せば自由な雰囲気の源でもあった。

【3歳の頃、お正月で着物姿の内田加奈と5歳の姉。旧海部町の自宅前(提供写真)】
▽閉じ込める病院
京都の病院では作業療法士として、精神疾患のある人たちの社会復帰をサポートしてきた。「早く一人前にならなければ」と周囲に適応するのに懸命だった。立ち止まって物を考える余裕もないまま時は過ぎ、2015年に「WRAP」というプログラムに出合った。
メンタルヘルス(心の健康)の回復プランから生まれたもので、どんな状態の時でも自分らしく生きられるように、自らの手で手引を作成する取り組みだ。人生の主導権を医療者から取り戻そうという動きでもある。
WRAPの理念を通してそれまでの仕事を見直すと、当然と考えていた病院の世界がとても恐ろしいものに思えてきた。
カンファレンスは医療者だけで行われ、患者不在のまま処遇が決められる。患者が人としてごく当たり前の主張をしても「具合が悪いのだろう」と判断され、薬の量だけが増やされる。
ある患者が「退院したい」と希望すると、逆に開放病棟から閉鎖病棟に移される場面も目撃した。「患者のため」という言葉は、病院に閉じ込めておく方便に聞こえた。
「自分は大事なことから目を背けてきたのかもしれない」。病院で仕事を続けるのが、次第に苦しくなっていった。
勤め始めた頃に抱いた素朴な疑問を思い出した。「この入院患者さん、海部で生活してたら普通に町を歩いてるやろな」

【パソコンで作業する内田加奈=神戸市】
▽ただそばにいる
ついに出勤もできなくなり、16年春に休職した。うつに近い状態で自宅の布団に引きこもった。
「私は社会人失格だ」と自分を責めた。だが、少し冷静になってみると「わが身を否定するのは日々接している患者さんを否定するのと同じではないか」と思い至った。
ある患者が「障害年金をもらうのはつらい」と話すのを聞き「権利なんだからもらえばいい」と口にしたことを恥じた。いざ自分が働けなくなってみると、権利と分かっていても失業保険をもらうのは心苦しかった。
結局、病院は辞めた。WRAPで知り合った仲間に悩みを打ち明けると、適度な距離を保ちながら支えてくれた。症状は少しずつ回復し、現在は神戸市の訪問看護ステーションに勤務しながら、患者宅を回っている。
家族にも悩みを語れず、1人で抱え込む人たちに出会いながら「ただそばにいる」というケアの在り方を考えるようになった。人は他者に依存して生きる存在だ。困っている時は助ける。でも、自分の生き方は自分で決めなければならない。
それは「つながりながら縛らない」という海部の人たちが大切にしてきた価値に似ている。理想の職業観は、故郷の原風景に刻まれていた。そのことにようやく気付いた。
(敬称略、文・名古谷隆彦、写真・藤井保政、2023年6月10日出稿、年齢や肩書は出稿当時)

【スタッフと打ち合わせする内田加奈(中央)=神戸市】