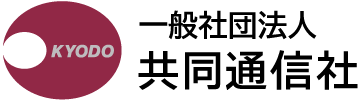長期連載‐国内
(9)放水指示、指揮官の宿命 「声なき声」聞き続ける
新井雄治(あらい・ゆうじ)(71)の義父は戦時中、茨城県の海軍航空隊で少年飛行兵を訓練する軍人だった。92歳で亡くなるまで、会えば特攻隊として送り出した若者たちのことを語ってくれた。「でも敵艦にたどり着く前に、みな撃墜されてしまったんだよ」
口ぶりからは後悔する様子がうかがえた。最後は自らも特攻を命じられたが、搭乗するはずの機体が出撃の直前に使えなくなり生き延びた。その太平洋戦争から60年余り。まさか自分が同じ苦悩を抱えることになるとは思いもしなかった。

【東京電力福島第1原発が望める福島県双葉町の海岸を訪れた新井雄治。「帰って来られないかもしれない場所に送り出した。とんでもないことをしてしまった」と当時を振り返る】
▽放水成功
2011年3月11日、東日本大震災が起きた。東京消防庁消防総監だった新井は、東京から200キロ離れた東京電力福島第1原発事故の対応に気をもんでいた。3号機の使用済み燃料プールの水が蒸発すれば、中にある燃料がむき出しになる。自衛隊や警察が注水のために出動したが、事態は好転しなかった。
東京消防庁に出動要請がかかるのは時間の問題だったが、原発事故対応は消防の仕事ではない。新井は隊員を送り出すのに抵抗があった。ただ第1原発が爆発し、大量の放射性物質が飛散すれば東京も無事ではすまない。若手は除外し、40歳以上の隊員だけで部隊を編成するよう命じた。
ところが、主力のハイパーレスキュー隊員は20~30代が中心で人数が足りない。若手に関しては本人の意向を尊重する形にして、139人の派遣部隊を整えた。「消防で働いている者たちだ。千人に1人も断らないだろう」。新井は心のどこかで高をくくっていた。後にその安易な値踏みにさいなまれることになる。
活動中に爆発が起きれば、隊員の大半が死ぬか重い障害を負うのは確実な作戦だ。細かく安全対策をしたところで、全員を無事に帰還させる自信はなかった。「特攻を命じてしまったかもしれない」。福島へ向かう隊列を見送ると、義父の顔が思い浮かんだ。
「放水成功」の連絡は19日未明に入った。放射線の被ばく線量も許容範囲内で、ひとまず胸をなで下ろした。

【2011年3月19日、東京電力福島第1原発3号機に放水する東京消防庁の「屈折放水塔車」(同庁提供)】

【東京電力福島第1原発事故の放水活動任務に当たった消防隊員ら=2011年3月18日夜(同庁提供)】
▽末端の現場
震災対応が一段落した数カ月後、新井は消防総監を退官した。消防の世界からは距離を置くつもりだったが、講演や手記を求められ、原発事故に引きずられる格好で古巣との付き合いは続いた。
15年夏、現地に派遣した隊員が肺がんのため55歳の若さで亡くなる不幸があった。原発事故時にはホースを抱え、車外で活動する部隊に所属していた。新井は放射線が原因ではないかと疑った。
主治医は影響を否定していたが、隊員も「被ばくのせいではないか」と気にかけていことを後に知った。自分の気付かぬところで、隊員たちは不安を抱え続けていた。
震災から5年となるのを前に、東京消防庁が震災時の隊員の体験談をまとめることになり、編さん委員に就いた。寄せられた手紙やメールを読むと「いっそ総監から出動を命じてほしかった」との一文に目が止まった。
ある消防署は派遣要請があった場合に備え、署員を集めて現場に行けるかどうか意思確認をしていた。署長が「行ってもよい者はいるか」と問うと、「行きます」と中隊長クラス3人のうち2人が手を挙げた。しかし、最も若い隊員は体を震わせながら「自分は行くことができない」と答えるのが精いっぱいだった。
翌朝、その隊員は署長の元を訪れ「行かなければ、この職場で仕事を続けていけない。要請があれば真っ先に出してほしい」と直訴したという。
夜通し悩み、参加を決めた者がいた。家族を心配させないように、現地の活動内容を伏せて福島に向かった者もいた。
末端の現場で、そんな葛藤が繰り広げられていたことを初めて知った。

【東京電力福島第1原発の放水に向かう隊員を手を握って送り出す新井雄治。「頼む、無事に帰ってきてくれ」との思いだった=2011年3月18日、東京都内】

【2011年3月、福島第1原発3号機への放水活動の打ち合わせをするハイパーレスキュー隊員ら(東京消防庁提供)】
▽「あんな作戦」
報告書には、成功した事案ばかりが記載されていたが、新井は「表に出てこない話があるに違いない」と気付いていた。
公式の聞き取りでは組織への遠慮が先に立ち、本音を話すことはできないだろう。震災から10年になるのを機に、新井は約10人の隊員に個人的に連絡を取ることにした。
ある中堅隊員は、この任務に部下を連れて行ったことをいまだに悔いていた。「あんな作戦は自分たちが断らなきゃいけなかった」。現場に行った者だけが味わう恐怖、中間で板挟みになった者の悲哀。ため込んでいた苦悩がぽろぽろとこぼれ落ちてくるようだった。
新井は多くの人に「あなたの判断は間違っていない。仕方がなかった」と言われた。隊員からは「参加して良かった」と伝えられたこともある。だが、若手に自主判断を求めるぐらいなら、自分の責任で命じるべきではなかったのか。
自問は今も続く。あの原発を放っておくことはできなかった。もし同様の局面が訪れたなら、今度も自分は「現場に行け」と命じるだろう。たとえ一生得心できない決断だとしても。
(敬称略、文・三吉聖悟、写真・堀誠、2023年3月4日出稿、年齢や肩書は出稿当時)