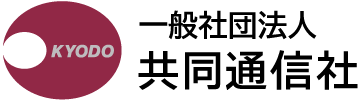長期連載‐国内
(8)資本主義への挑戦敗れ 「全員参加」に託した夢
人前で言葉が詰まるのは初めての経験だった。2018年6月、東京都足立区の印刷会社「ミツノ」の社長、田中克治(たなか・かつじ)(68)は、食堂に集めた9人の従業員に倒産を告げた。「悔しいけれど、終わりを決断せざるを得ませんでした」

【仕事の行き帰りに立ち寄る散歩道。下町の風情が残る路地と奥に見えるスカイツリーが気に入っている=東京都墨田区】
02年に発足した会社は労働組合が母体だった。株式会社だが出資者は全員従業員で、それぞれの意見を経営に反映させる労働者協同組合の理念を掲げた。トップダウンでなく、責任をみんなで分かち合う合議による運営を目指し、設立趣意書では「労使紛争からの解放」をうたった。
長年、労働運動に身を置いた田中にとって、自主経営は弱肉強食の資本主義社会への挑戦だった。ただ、それは経営者と労働者という異質な立場の間で揺れ動く、葛藤の始まりでもあった。
▽自由の空気
福岡・筑豊の炭鉱住宅の長屋で育った。みんな貧しかったが、どの親もよその家の子どもにも食事を分け与え、遠慮なく〓(口ヘンに七)る共同体だった。
高校2年で、福岡市の県立福岡高校に転入すると、都会には自由の空気が漂っていた。仲間に誘われマルクス・エンゲルスを読んでみたり、沖縄返還協定反対のデモに参加したりした。幼いころから貧しさを目の当たりにしてきた田中には、自分が学びたいことがそこにあった。
進学した静岡大でも学生運動に没頭。やがて就職の時期を迎えると、自分で労組を組織して職場環境を良くしたいと考え、労組のない中小企業への就職を目指した。
印刷工場は長時間労働、低賃金の職場だったが、確かな技術が求められる仕事は楽しかった。早く一人前になりたい気持ちが勝り、労組をつくるのは先のことだと思っていた。
1年後、事件があった。賃上げの延期に怒った従業員が一斉に職場放棄し、田中が首謀者と見なされ解雇されたのだ。思いがけぬ形で労組を結成することになり、撤回を勝ち取った。
その後は、社内の労働条件の改善だけでなく、社会全体の問題に目を向けるため、外部の労働争議を積極的に支援した。

【集会でマイクを握る田中克治(提供写真)】

【移転した工場の開所式であいさつする田中克治=2014年2月、東京都足立区(提供写真)】
▽理念の形骸化
1990年代後半、出版事業が先細りし、経営陣は黒字のうちに工場を廃業する意向を示した。
労組幹部だった田中は会社側と交渉を重ね、家賃を支払う代わりに機材を安価で買い取り、新会社を設立した。確たる勝算はなかったが、従業員の雇用を守りたかった。
外部の労組の仲間からは「経営と労組は別だ。経営者らしくならないと事業は失敗する」と忠告を受けた。田中は「気持ちは労働者側にある」と言い返した。新しい会社では労使問題は絶対に起きないと信じていた。
当初は順調にみえた経営はやがて暗転する。リーマン・ショック、東日本大震災によって需要が後退。勃興したネット印刷に、価格で対抗するのも難しかった。
月に1度、経営状況を公開し、改善点や方向性を話し合う会議は、ミスをした従業員を別の従業員が責任追及する場に変わった。田中は厳しい現実を伝えることに尻込みし、問題を抱え込むようになった。全員参加の理念は形骸化した。
自身の報酬を下げ、私財を投入し、借金をしても業績は改善しない。従業員の賃下げや人員削減という「禁じ手」に手を付けざるを得なくなった。「なりふり構わずだね。最初の志なんて、へでもなくなっていた」。一部の従業員とは口もきけない状態になった。
交渉の場ではひたすら怒号に耐えた。「自分が同じ立場なら同じように突き上げる。それだけのことを強いた」
▽経営者の孤独
労働条件切り下げの通知文は深夜、静まりかえった事務所に残ってつくった。さまざまな思いが去来した。今後の妻との関係はどうなるのか、母親が存命のうちに倒産し「がっかりさせたくない」との願いもあった。経営者の孤独とはこういうことなのかと知った。
倒産を伝えた時、従業員からは何の声も上がらなかった。どう受け止めてよいか分からず、言葉にならないのだと思った。取引先に頭を下げ、再就職を決められたのが、せめてもの田中の罪滅ぼしだった。
描いた理想をどうすれば実現できたのか、今も考える。印刷業界への逆風は失敗の大きな要因ではあったが「雇う者と雇われる者、決める人と従う人。その溝を埋めることは、どうやってもできないのかもしれない」と敗北感も頭をもたげる。

【移転前の工場跡地(左奥)を訪ねた田中克治。近所の桜や都電など思い出を語った=東京都荒川区】

【夜勤明けに勤務先の福祉施設前で笑顔を見せる田中克治=東京都墨田区】
田中は今、都内の福祉施設で、老齢の元日雇い労働者らのケアに従事し、休日はフードパントリーを仲間と開く。経済的な困窮だけでなく、地縁も血縁もなくした人たちと関わり、自分はいかに世の中を知らなかったか痛感した。「そう簡単に心は開いてくれない。でも、丁寧に接していると『ありがとう』って言ってもらえる時があるんだよ」。印刷工場時代とは別の生きがいがそこにはある。
(敬称略、文・小島孝之、写真・今里彰利、2023年2月25日出稿、年齢や肩書は出稿当時)