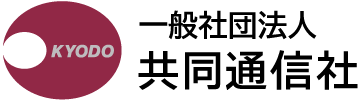長期連載‐国内
(7)暗闇から、春の日だまり 震災契機、手にした白杖
吉田千寿子(よしだ・ちじゅこ)(86)は、滑らかな手つきでティッシュを着物の襟元の形に折り畳んでいく。「肌さ沿うように、端をキュッと」。東日本大震災後に移り住んだ岩手県陸前高田市の自宅の居間。修業時代、師匠の着付けをまねて繰り返した手技が、視力を失った今も身に染みている。

【津波で流された自宅があった場所を訪れた吉田千寿子。跡地は草で覆われていた=岩手県陸前高田市】
▽魔法
幼かった日、陸前高田市広田町の実家近くで偶然見かけた花嫁の姿に魅了された。真っ黒の留め袖、色鮮やかな帯。「質素だけど、華やかで」。中学卒業後、美容師に弟子入りし、住み込みで技術を身に付けた。
20代半ばの春、地元で美容室を開く。その日、庭先に咲いたタンポポに「頑張んねば」と誓った。カットやパーマだけでなく、花嫁にヘアメークを施し、着付けて晴れ舞台に送り出す。「魔法がかかったようにきれいになるの」。誇らしさが胸にあふれる。
46歳のある日。いつものように店に立ち、お客さんの右眉を描いていたら、眉山を境に耳側の視界が急になくなった。まばたきするうちに戻ったが、不安に襲われた。
診断結果は緑内障。徐々に視力が低下し、いずれ両目とも見えなくなると告げられた。「今日はあそこまで見える。だけど1週間後にはどうなの」。誰もいない部屋で、手のひらで目を覆い、光のない世界を想像する。「死にたい」と思った。
スタッフ全員の働き先が決まった後で、生きがいだった店を閉めた。56歳になった吉田は、左目を失明していた。
視覚障害者であることを周囲に示す意味もある白杖(はくじょう)。市に申請して手元に置いたが、使うことはできなかった。特に近所は絶対だめだ。美容師時代を知る人に見られることは耐えられなかった。人の手など借りたくはない。家にこもりがちになった。
新たな病魔が追い打ちを掛ける。2010年8月。突然、自宅トイレで腹痛に襲われ、気を失った。救急搬送され、8時間に及ぶ手術を受けた。診断は大腸がん。医師から、余命数カ月と告げられた。右目の視力は、かろうじて光を感じる程度に衰えていた。

【1997年、当時の自宅の居間で夫の高治(右)と笑顔で話す吉田千寿子。娘が写した1枚=岩手県陸前高田市(提供写真)】

【千寿子が自身の震災体験を記した絵本】
▽巾着袋
自宅で療養中だった11年3月11日、震災が起きた。同居の娘は仕事に出ていて一人きり。ベッドに寝たきりの状態だった吉田は、激震の中、やっとの思いで起き上がり、四つんばいで掘りごたつの下に潜り込んだ。
「助けを求めても、人に迷惑をかけるだけ。生きていても何の役にも立たない。このまま死んだ方が良いのでは」。家族の顔が走馬灯のように脳裏に浮かんだ。
たんすから何かが落ちた。手で探ると、抗がん剤が入った巾着袋。飲まないと命はないと言われていた。その手触りに「大切なものだ」との思いがこみ上げ、とっさに胸に抱えた。「逃げもせずに死ねば、家族が悔やむかもしれない」。巾着袋を握り締めて外に出た。
「逃げろ、逃げろ」と叫ぶ声。子どもが泣いている。猛スピードで走り去る車の音、クラクション。庭に立つ吉田に声をかける人はいなかった。
急に静寂が訪れた。音のない世界に恐怖がこみ上げる。
「かよちゃーん」
たまらなくなって、向かいに住む友人に助けを求めた。気付いた友人に手を引かれ、近くの寺に避難できた。「あんたも生きてた」「いがったな」。近所の人たちと抱き合って無事を喜んだ。
自宅は津波で流され、寺で2カ月半に及ぶ避難生活を送った。最初はこれまで通り、見えないのに、見えているふりをしていた。だが慣れない場所での暮らしで、娘もずっと付き添ってはいられず、限界を感じるようになった。
白杖は津波で流されたが、支援者が新しいものをくれた。ある日、手に取って寺の中を歩いていたら「それ何なの」と子どもの声。「ばあちゃんの目だよ」。とっさに答えていた。それからは廊下で迷っていると、子どもが声をかけて導いてくれるようになった。
寺を出て仮設住宅に移るころには「人の手を借りながら、生きられるだけ生きてみよう」と思えるようになっていた。

【高台に建てた新しい家の居間で、震災当時を振り返る吉田千寿子】

【津波で流された自宅跡を訪れた後、車窓から海を眺める吉田千寿子=岩手県陸前高田市】
▽春のにおい
あれから12年、右目の光も失った。一日の大半を自室で過ごす吉田の楽しみは、頭の中で体験を基にした絵本をつくることだ。
昨春、親族が聞き取って二つの物語にまとめ、イラストを添えて製本してくれた。それぞれ数冊だけのささやかなものだが、吉田は気にするそぶりもなく「生きている証しを置いて逝く」と無邪気に笑う。
主人公は目が見えない「ちいばあちゃん」。一つは震災の日の物語。もう一つでは、震災を生き延び、ボランティアに手を引かれ、花見に出かける。「ふんわり、ふかふかするような、春のにおいがする道を、一歩また一歩と進みます。なんて気持ちのいい、あたたかな春の日だろう」
(敬称略、文・大石祐華、写真・鷺沢伊織、2023年2月18日出稿、年齢や肩書は出稿当時)