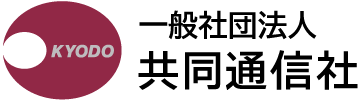長期連載‐国内
(6)わが子の思いに近づきたい 後悔の念、登山の道へ
あの日の朝は雪が降っていなかった。「学校まで送ろうか」。浅井道子(あさい・みちこ)(57)が息子譲(ゆずる)にかけた最後の言葉は、いつもの何げない一言だった。「いや、大丈夫」。そう言って自転車に飛び乗った譲が雪山から帰ってくることはなかった。2日後のほぼ同時刻、雪崩が起きた。高校2年生の17歳。早すぎる死だった。

【山岳部のトレーニングで登った日光白根山山頂で笑顔の浅井譲さん=2016年6月(提供写真)】
▽父の背中
2017年3月27日午前、栃木県那須町で高校生ら計8人が犠牲となった。県高等学校体育連盟主催の登山講習会に参加した県立大田原高の生徒と教員で、譲もその一人だった。
午前10時過ぎ、那須塩原市内で勤務していた道子の携帯が鳴った。小学生だった娘の千鶴(ちづる)(16)からだった。「高校から電話あったよ」。しばらくして、何台もの消防車と救急車がけたたましく走る音が聞こえてきた。
「高校生が雪崩に巻き込まれ、心肺停止だって」。ニュースを見た同僚の一言で道子は職場を飛び出した。後輩の先導役をしているはずの譲は、駄目かもしれない。直感的にそう思った。
搬送先の病院に行くと譲が横たわっており、体は冷たかった。左手の甲にはボールペンで「水」の文字がにじんでいた。水を忘れた後輩のために、いつも自分が数リットル多く持っていく子だった。
譲が山に登り始めたのは6歳。自発的というよりも高校、大学と山岳部だった夫慎二(しんじ)(53)が、半ば強引に連れ回したからだった。譲は黙々と慎二の後を歩き、一切弱音を吐かなかった。
「山岳部に入ろうかな」。高校に入学して間もなく、ふと相談してきた。以降、週末になると夫が愛用していたウエアを身にまとい、県内外の山に挑んだ。道子は譲が慎二の背中を追いかけているように思えた。

【閉鎖されている那須ファミリースキー場の奥に見える茶臼岳の山腹。2017年3月、中央左上の斜面で雪崩事故が発生し、春山登山講習会に参加していた高校生7名と教員1名が犠牲となった=栃木県那須町】

【自宅の和室で譲さんの祭壇に向かう浅井道子(左)、慎二夫妻=栃木県那須塩原市】
▽信頼関係
だが、雪崩事故が全てを変えた。朝起きると、譲がいない現実を突き付けられる。夕暮れ時、帰宅途中の高校生を見ると自然と涙が頰を伝った。心を病まないようにと心理学を勉強して気持ちを落ち着かせた。
譲が読んでいた本を片っ端から図書館で探し、出場したマラソン大会でも同じコースを走ってみた。何を考えていたのか、少しでも理解したかった。そんな時間だけは悲しみを忘れることができた。
安全講習はきちんと行われたのか。元顧問らに雪崩の知識はあったのか。漫然と指導していたのではないか。元顧問から届いた手紙を見ずに、破り捨てたこともあった。
怒りの感情と同じくらい後悔の念も持ち続けた。「あの朝、なんで学校に中止を求める連絡をしなかったんだろう」
気持ちが変化し始めたのは、1年後の事故現場近くで行われた追悼式だった。雪解けで輝く那須山を見上げると、コバルトブルーの空が広がっていた。「譲はここで笑って過ごしているんだ」と思うことにした。
登山経験が少ない道子だったが、少しずつ山に足を運ぶようになった。大田原高山岳部OB会が部活を見守る活動にも、21年夏から参加し始めた。後輩を大切にした譲の思いを引き継ぎたかった。「事故で廃部になったら、悲しむかなと思って」。山道を歩くとふわふわと付いてきて見守ってくれている気がした。
同行しながら山岳部の活動の一端を垣間見た。顧問は事前に山頂まで登って安全を確かめ、生徒のけがを想定して何十キロもの荷物を背負っていた。部員は顧問の背中を見て進む。厳しさの中に信頼関係が見て取れた。
譲たちもこんな関係だったのだろうか。「山の師匠」と慕っていた元顧問と銭湯やラーメン屋に行ったことを、譲が楽しそうに話していた姿を思い出した。

【家族でトレッキングした栃木県塩谷町の尚仁沢で写真に納まる(左から)譲、千鶴、慎二。セルフタイマーで写した1枚=2015年5月(提供写真)】

【茶臼岳の登山道を行く浅井夫妻。「疲れても口に出さない子でした」。道子は小学生の譲と登った記憶をたどった。慎二は息子の山靴を履いている。夫妻は大田原高山岳部の見守り隊に参加、那須の山々を歩いている=栃木県那須町】
▽捨てた憎しみ
昨年、5遺族が県や元教員などに損害賠償を求めて提訴した。だが、浅井家が裁判に加わることはなかった。裁判を通じて事故と向き合う遺族もいるのは理解している。ただ、道子は憎み続けるよりも、その分のエネルギーを登山にぶつけた。慎二も同じ思いだった。「憎む気持ちは捨てたかったんです。それが生きる原動力にはなりませんでした」
夫婦は昨年末、業務上過失致死傷罪に問われた被告の教員3人の公判に出席した。元顧問は終始無言で目をつぶっていた。
道子はもし話す機会があれば、ずっと言いたいことがあった。「先生と山登りしたいです。今後どうしたら事故が起きないか、山で生徒たちと一緒に考えましょうよ」
ある日、にぎわいが去ったリビングで娘の千鶴がつぶやいた。「やっぱり4人がいいね」。道子は、はっとした。この5年間「遺族」と呼ばれ続け、夫と娘の3人暮らしに無理やり慣れようとしていた自分に気付いた。
無理して生きる必要はない。登山と同じだ。休みながら一歩ずつ、私たち家族のペースで歩んでいけばいい。一辺が空席のこたつを見て、そう思った。
(敬称略、文・待山祥平、写真・京極恒太、2023年2月11日出稿、年齢や肩書は出稿当時)