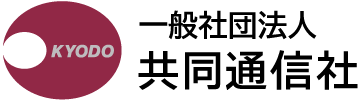長期連載‐国内
(1)「あれはドラマですから」 沈黙14年、ほどけた心
場面が進むにつれ、違和感が募っていく。1999年にダウン症の息子、秋雪(あきゆき)を亡くした写真家の加藤浩美(かとう・ひろみ)(58)は、それから5年後、息子を主人公にしたドラマの完成試写会に臨んでいた。「これは本当に秋雪の物語なんだろうか」。脚色された内容に戸惑った。

【1998年夏、茨城県の大洗海岸で加藤浩美が撮影した秋雪と夫のツーショットはCMにも使われた。加藤には夫が秋雪に抱かれているように見える(ⓒ加藤浩美)】
数歩歩くのがやっとだった病気の息子が、画面の中では走っている。母親が将来を悲観して入水自殺を図るシーンには、さすがに腹が立った。子どもを残して自分が命を絶つわけがないだろう。
家族の真の姿が、人の手でねじ曲げられたように感じられ苦しかった。でも自分が批判的な言動をすれば、ドラマに関わってくれた人たちは傷つくかもしれない。以来、加藤は何を聞かれても「あれはドラマですから」としか語らなくなった。
▽1万枚の写真
92年秋に生まれた秋雪は、心内膜床欠損症を伴うダウン症で「余命1年」と診断された。生後1カ月のことだ。飲む力が弱く、ミルクを吸うと全力疾走した後のように汗をかいた。不安と隣り合わせだったが、つかまり立ちができるようになり、立ち上がり、そして7歩歩けるようになった。
息子の生きた証しを残したいと思った加藤は、亡くなる99年1月までに1万枚の写真を撮った。4年後には写真入りの手記「たったひとつのたからもの」を出版。息子の写真はCMにも使われ、大きな話題を呼んだ。
加藤には自著を通じて訴えたい思いがあった。同じダウン症児でも、他に重い病気を抱えている子と元気な子では育て方が違う。同じような境遇の人たちに、少しでも参考になればと考えた。
6年間にわたる家族3人の濃密な日々が伝われば、秋雪の人生は短くはなかったと感じてもらえると思った。

【お気に入りの椅子に座る秋雪=1995年5月、埼玉県の自宅(ⓒ加藤浩美)】
ドラマ化を承諾した際、加藤は原作が脚色されることは頭では理解していた。しかし実際に映像に向き合うと、心がかき乱され、どうにも整理がつかなくなった。
秋雪役は、年代順に3人のダウン症児が懸命に演じてくれた。多くの関係者が良い作品にしようと努力し、視聴率も30%を超えた。そうした経緯を知るだけに、加藤は「自分さえ黙っていればいい」と喜怒哀楽を表に出せなくなってしまった。
わが子を失ってから、ずっと拭えない感情があった。「この喪失感や苦しみは、結局のところ他人には分かってもらえない」。ドラマはその象徴的な存在として、加藤を縛ることになった。
▽撮影仲間
秋雪は96年春、自宅にほど近い埼玉県桶川市の「いずみの学園」に入園した。障害のある子らを受け入れており、保育士や保護者も一緒になって成長を見守ってくれた。
秋雪が亡くなった後も関係は続き、園の様子をボランティアで撮るのが加藤の日常になった。しかし時の経過とともに秋雪を知る人はいなくなり、園児の写真撮影に抵抗を示す保護者も現れた。
秋雪の思い出が詰まった大切な園とも次第に疎遠になり、加藤は社会との大きな接点を失った。
被写体を求めて、各地に車を走らせた。特に思い入れが強かったのは、秋雪と夫をツーショットに収めた茨城県の大洗海岸の風景だ。

【日の出を撮影するために思い出の場所を訪れた写真家の加藤浩美。息子、秋雪を撮り続けたフィルムカメラを慈しむように両手で包み込んだ=茨城県大洗町】
撮影は1人で行くことが多かったが、自分の本を読んでくれた同年代の女性と知り合いカメラ仲間になった。秋雪が取り持ってくれた縁だった。
片道約3時間かかる車の道のりは、気の合う相手でないと間が持たない。いつも他人の出方をうかがうようになっていた加藤とは正反対に、女性は気軽に間合いを飛び越えてきた。その遠慮のなさが心地よかった。
「今は園の撮影に行くのがつらい」と正直に打ち明けると、彼女は「嫌ならやめちゃえば」ときっぱり言い放った。自分の迷いを見透かされ、同時にそっと背中を押してくれる。「もっと人に弱音を吐いてもいいのかも」。身内には言えない話でも、彼女には何でも相談することができた。

【秋雪をあやす加藤浩美=1994年5月(ⓒ加藤浩美)】
▽穏やかな心
2018年秋、加藤は京都司法書士会の座談会にゲストで呼ばれた。小さな部屋に参加者は4人。和やかな雰囲気の中、子を持つ母親に秋雪の子育てについて語った。話題はドラマにも及んだ。
「実は私はあのドラマには引っかかりがあります。とてもつらかった」
わずか4人の前だったが、加藤は公の場で14年間の沈黙を破った。墓場まで持って行くと決めていたのに、素直に本心を口にすることができた。
参加者の母親は「ドラマを見た後に本を読んでくれた人もいたんでしょ。分かる人には分かってもらえるから大丈夫」と温かく応じてくれた。
「かたくなに語らないと決めつける必要はなかった。受け止めてくれる人はちゃんといる」。でも、それが分かるには長い時間が必要だった。
加藤は最近、撮りためた写真の整理を始めた。シャッターを切る瞬間に封じ込めた感情を、秋雪の表情とともに思い出す。深夜まで没頭すると、穏やかな心が戻ってくる。
(敬称略、文・名古谷隆彦、写真・今里彰利、2023年1月7日出稿、年齢や肩書は出稿当時)

【撮りためた秋雪の写真を整理する加藤浩美】